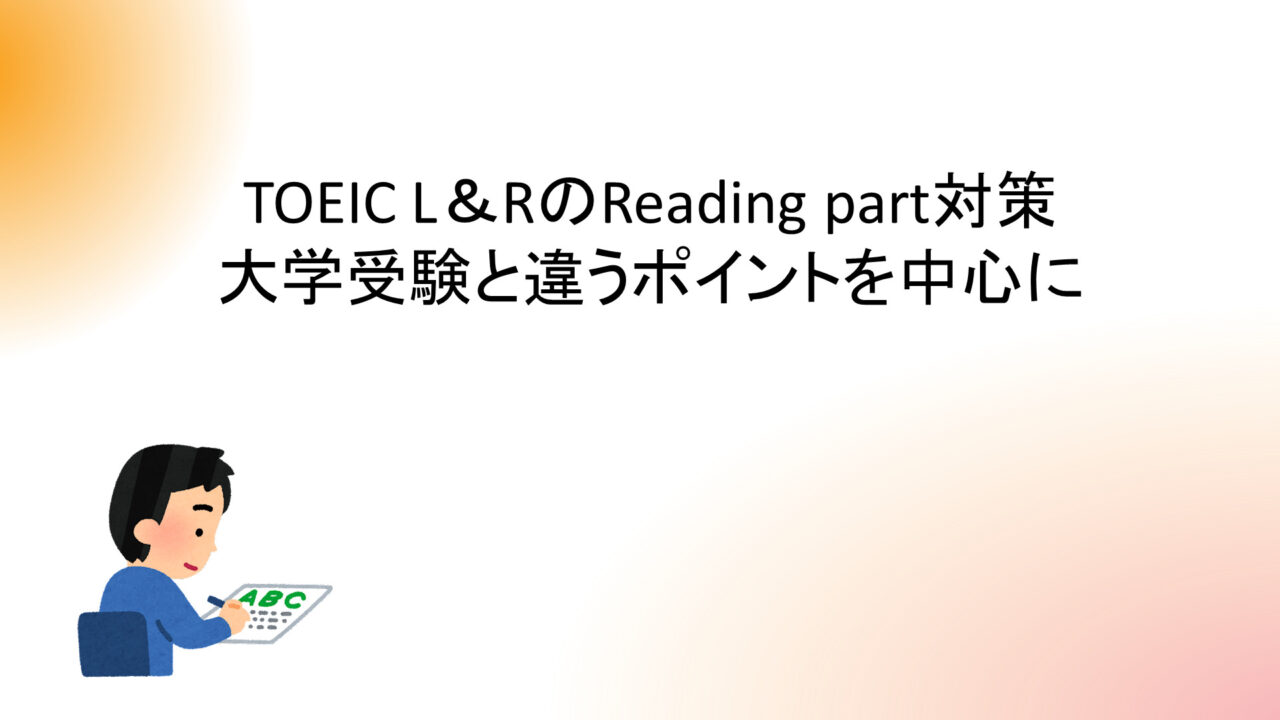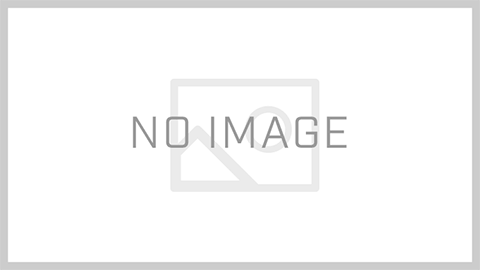みなさまこんばんは、あのつぎはイです。今日も更新やっていきます。
今日の更新は、表題の通りTOEIC L&R(以下TOEIC)のうちReading part対策について、中学英語や大学受験との違いとかお話ししたいと思います。
特に今回は次のような方に読んでいただきたいと思います。
- 大学受験が終わった大学生だけど、TOEICって専用の対策をせずに高得点が取れるのか知りたい人
- 中学や高校時代に使っていた英語の参考書や問題集が残っており、これがTOEIC対策に転用できるか知りたい人
- 中学高校時代はあんまり英語が得意ではなく、今からTOEICを受験する上でどこから手を付けたらいいか分からない人
自分自身は大学受験を経験した直後の大学1年生の冬(大学受験からちょうど1年)にTOEICを初めて受験して、730点でした。何とも中途半端な点数でしたね。
その時の経験を思い出しながら、またその後社会人としてTOEIC対策をしていくうちに感じるようになったTOEICと大学受験の英語との違いを今回は話の中に混ぜていければいいかなと思っています。
主に以下のように分けて説明していこうと思います。
- TOEICと学校英語の類似点と相違点
- 英単語
- 英文法
- 長文
それではさっそくやっていきましょう。
なお、Listeningについては下の記事を参考にしていただけると嬉しいです。それから英語学習をするうえで、4技能ではなく4分野で分けた方が良いという記事も書いたので、そちらも見てもらえると、この記事の本文の理解が早まると思います。
TOEICと学校英語の類似点と相違点
まずはTOEICと学校英語の類似点と相違点について説明していきます。といっても、大雑把に言うと
類似点:勉強する大枠は変わらない、中学英語は全ての英語学習の基礎
相違点:出題頻度に差がある(特にTOEICと大学の個別受験)
ここで強調したいのはTOEICにしてもTOEFLにしても、どんな英語資格でも共通して言えることとして、
中学英語が8-9割以上理解できていることが前提=中学英語が不安ならまず中学英語を勉強しよう

という物です。高校はいいです、気にしないでください。
これを、単語、文法、長文の3分野に分けて説明していこうと思います。
英単語
まずは英単語から。
こちらについては下のようになります。
- 中学レベルの英単語や英単語帳
TOEICの基礎となる単語が多いため、8割以上覚えていなければ覚えなおし - 高校の教科書
ビジネスに関する項目は知っておいた方が良い - 大学受験用の英単語帳
あまり被らないためお勧めしない - TOEIC専用の英単語帳
レベル別で少し違うものの、用意することをおススメ
順番に説明していきましょう。
中学レベルの英単語や英単語帳
日本の中学英語の範囲って、かなり良くできていて、これだけで実は日常会話もできるレベルです。勿論中学レベルの英単語はTOEICでもほぼほぼ必須です。
といいながら、これ人によっては反論する人もいるんですよ。中学の英単語はTOEICには出ないって(試験としての意味で)。
でもね、これとんでもない落とし穴なんですよ。
というのも、例えばTOEIC専用の参考書とかって、よほど基本的な所から解説している物でもない限り、というか初心者用と謳っている参考書ですら「中学英単語は知っていて当然(もしくは中学英語でつまずきやすいところから解説する)」を前提としているため、もし中学英単語を知らないレベルの初心者の場合は、本の内容を理解する上で非常につらい思いをすることになります。
なのでTOEICを勉強しようとしている人は、まず中学レベルの英単語を覚えているかどうかを確認すると良いです。writingをする訳ではないので、英単語をかける必要はないですが、英語→日本語訳は知っていてください。
手元に中学教科書がある人なら、一度音読してみて単語の意味は苦に無くとらえることができるかどうかチェックしてみて、知らない単語があればAnkiで覚える(使い方などはこちらの過去記事から)、高校受験などで使った英単語帳があれば、まずその単語帳をめくって8割以上覚えているか確認してみるというのが上手な使い方ですね。
高校の教科書 大学受験用の英単語帳
先に述べたように中学英単語はほぼほぼ必須と言っておきながら、高校になっただけで評価が変わります。高校もしくは大学受験で出てくる「ビジネス英語」はTOEICでも基礎的なレベルかもしれませんが、一方でビジネス以外の英単語についてはTOEICにほぼ出ません。例えば生物学的な英単語(bloodとかreptileとか)は、大学受験だと出ても不思議ではないですが、TOEICでは稀か、出たら難単語の扱いとなるかといった感じで、頻出かどうかに差が出てきます。
そのため、TOEICで高得点を取りたいというのが目標であれば別ですが、TOEICの勉強を考えている人で、中学レベルは大丈夫→高校レベルをチェックしてみようと思って高校の教科書や大学受験の英単語帳を活用するのは少し待ってみた方が良いかもしれません。
TOEIC専用の英単語帳
単語の最後はこちら。中学レベルがクリアできていれば、個人的にはその次のレベルに合わせて英単語帳を用意した方が良いかと思います。
その時にどうするかというと、英単語を考える前に、まずTOEICの公式問題集(最新版がベスト)を解いてから考えてみてもいいと思います。
公式問題集を解いてみて、知らない英単語が多くて困ったなーと思えば、tex加藤先生が朝日出版より出している銀のフレーズ、金のフレーズ、金のセンテンスから1冊を選んで勉強すればいいかなと思います。
上の3冊からどれを選べばいいかという基準の一つとして
数ページ眺めてみて、知っている単語は大体5割前後ある
英単語帳を選ぶのがコツです。知っている単語が4割以下の英単語帳だと、勉強する上で負荷が強くて挫折します(断言します)。必ず5-6割知っている英単語帳を選びましょう。
英文法
ここはかなり気を付けた方が良い分野です。
というのも、自分の場合は、今でいうEvergreen、昔のForest(桐原出版)という辞書みたいな英文法書を高校時代にべったり勉強した経験があり、そのおかげで受験だろうが英検だろうがTOEICだろうが、おおよそ文法と言われる項目については出題の仕方さえ学んでしまえば対処できてしまうという、overwork気味の勉強をしてきたからです。
ということで、ここも中学英語と高校/受験英語との違いを説明したいと思います。
なお、世間では学校英語とか日常英語とかに異常な反応をします方々がいらっしゃいますが、このサイトでは便宜上上のような書き方をしているだけで
英文法に学校英語とか受験英語とか日常英語とかの違いはない!
と考えています。
違いが出るのは
出題頻度や使用頻度の違い
というのが自分の考え方です、だから勉強する重要度に違いが出ると考えてください。ここも強調しておきます。 では続けていきます。
中学英文法とTOEIC
ここは英単語と同じです。中学で勉強する英文法の項目は、文字通り義務教育です(笑)。知らないと危険です。
そしてここで注意してほしいこととしては、
「中学レベルの英文法の問題が解ける」と「中学英文法が理解/暗記できている」とは違います
という物です。
個人的には「中学英文法が理解/暗記できている」というのは、「中学レベルの英文を見た時に、使われている英文法項目を過不足なく説明できる」というレベルです。
例えば
My grandfather lives in the house which has a red roof.
という英文には少なくとも「3人称単数現在形のs」「代名詞(主格、目的格、所有格)」「5文型」「前置詞」「定冠詞」「関係代名詞」「不定冠詞」「形容詞」「名詞(加算、不加算)」といった文法項目が登場します。そのそれぞれについて、きちんと説明できるかどうか(例:liveという動詞について、祖父という私でもあなたでもない3人称の主語に対する動詞で、かつgrandfatherはsがついてないから単数でしかも今の話をしているからliveにはsを付けなければならない=3人称単数現在形のs)を個別に考えていく。
ところが一方で、学校(特に公立)によっては中学時代は文法用語を一切使わないところがあるので、場合によっては薄くても何でもいいので中学英文法を一度さらった方が良いかもしれません。
高校、大学受験の英文法
ここについては、中学とがらりと意見が変わり、語弊を恐れずに言えば
TOEICの対策をしたいのであれば、高校・大学受験の英文法書を活用しない方が良い
となります。理由は簡単で
項目は同じだが、頻出範囲が全然違う
からです。
だから、頻度に関係なくべったり勉強すれば、TOEICだろうが受験だろうが通用します。でも、TOEICを必要とする大多数は効率的に短期間で目標点数(昇進要件とか)を目指す人だと思うので、ここはTOEICに特化した方が良いです。
具体例を出せば、TOEICのpart5のような、4or5択から選ぶ文法問題であっても
- TOEICで頻出
品詞問題(名詞、形容詞、動詞など)、動詞の活用(現在形、過去形、ing形、過去分詞形など)など - 大学受験
関係詞、比較、省略、倒置など
というところで、全然出題範囲が違うんですね。同じ範囲から出るとTOEICでも大学受験でも似たような問題なんですけどね。
そこで、問題を利用して勉強したいのであれば、公式問題集に加えて花田先生が朝日出版から出している文法特急がおススメです(楽天市場に飛ぶとやたらに高い本が出てきますが、楽天ブックスに移動してもらえれば正規の値段が出てくると思います、どうなってんだ?)。
高得点を目指す人であれば、tex加藤先生が出している通称「でる1000」がおススメです。
文法の良い所は、時代が変わっても説明の仕方が変わらない事です。物の名前が名詞から形容詞に変わったら大事件ですからね笑。なので、例えば文法問題はブックオフとかで薄いものを購入して勉強するでもありかなと思っています。
長文
ここは、最近の共通テストを見ていると、だいぶ大学受験の基礎の所でTOEICに似てきたなーというのが個人的な感想です。それでも注意点がありますが。
長文を勉強する上で、必要になる「スキル」が違うと分かっていれば、どんな長文問題でも応用ができるはずです。そのスキルの違いというのは
- TOEICの長文問題
解答ポイントを如何に素早く見つけ出すか=ウォーリーを探せ - 大学受験の長文問題
難しい一文を正確に読めているか、文と文のつながりを理解できているか=論文を読む大学院生
なので、受験時代に解いていた共通テストやセンター試験の長文があれば(もしくはこの辺りの過去問が手元にあるのなら)、それを音読する(方法としてはこちらの記事がおススメ)事で早く読む練習になりますし、逆にTOEICの文章を読みながら、文と文のつながりや難しい構文をきちんと把握する練習をすれば(TOEICの文にあまり難しいものが無いですが)受験勉強にもつながります。
ちなみに、上の文を書いたからと言って、TOEICの対策のために「今から」東〇とかでセンター試験や共通テストの過去問を利用するのは、止めましょう。それくらいなら公式問題集を活用してください。
今まで長文を勉強したことが無いという方は、長文の読み方だけではなく解き方も知った方が良いと思う(ウォーリーを探すテクニックを知っていた方が早いでしょ?)ので、例えば究極のゼミなどを活用してもいいかもしれません・・・が、公式で実地研修(OJT= on the job training)をおススメしますが。
まとめ
いかがだったでしょうか。今日の記事は、TOEIC L&R(以下TOEIC)のうちReading part対策について、中学英語や大学受験との違いとかお話ししました。大事なことは
- まずはどの分野でも中学英語は必須
手持ちの中学教科書や問題集などをざっとやり直し - 高校大学受験の参考書とかは頻出が異なるので非効率
できればTOEIC専用を:やはり公式問題集が大正義
です。
皆さんが効率的にTOEIC対策ができることを願っています。
それでは今日はこの辺で、have a nice day and see you next day!